先日、インターナショナルスクールの見学会に参加してきました。
私が教わってきたような
この間行ったボランティア先の小学校のような
静かに授業を聞くスタイルではなく
子ども達が声を出して授業に参加し
中には席を立って黒板に書かれたものを指差し質問したりする子も。
決して静かではないのだけど、目的はみんな学びで。
授業の内容に対してみんなが声をあげてて。
頭の中で「あ!これ対話!対話スタイル!ソクラテス!」ってなった。
「おしゃべりはダメ」で学んできた私は
「授業に対することはどんどん発言して」
って子どもたちに伝えれば
おしゃべり減るんじゃないかなって思った。
学びの場が
「受け身の情報受け取り」ではなく「主体的な創造・対話」。
ソクラテスが見てたらきっと喜ぶだろうな。
大人が見守る環境の中で
子ども達が自分の言葉で考えを表現し
友達の意見を受け止め、そこからまた深掘りしていく姿には
学ぶことの本質が凝縮されているようにも見えて。
先生達の子どもの発言を拾って上手に返す器量にも驚きだった。
拾っていい塩梅で深掘りしたり
答えになってないような発言まで
上手に受け入れ繋げてくれる。
この授業、教科書の内容だけでなく
自らの観察力と表現力も育まれているのかもと。
先生が与える本の内容に対して
ただ受け止めるのではなく観察して自分なりの考えを持つ。
情報過多のこの時代にはすごく大切な感覚。
友達同士はもちろんだけど
先生と生徒の間でも
「切磋琢磨」するような姿もいいなと思った。
先生が絶対で完璧であるべき固定観念はここにはなくて
近くの大人が共に学んで共に成長するような姿って
きっと子どもたちのいい人間像になるんだろうな。
近くにいる大人の存在って結構大きい。
大人も失敗するし大人も成長し続ける
そんな姿を見せていきたいなと改めて思った。
色々考えるうちに
教育って知識の伝達だけでなく
子どもたちの「価値観」や
子どもたちの「生きる」を形づくる力を持っているという考えに。
そうとなると
日本の未だ続く「点数至上主義」みたいなものって
子どもたちの心にどんな影響があるんだろう?
教育が子供達に与える価値観って?
不登校が増えるのは無理もないのでは?
「生きる」を学ぶ場を求めてるんじゃない?
なんて色々考えて。
そして何より学校に頼るだけでなく
親として子どもに関わる大人として
自らも学び続ける姿勢を大切にすること
絶対に忘れちゃいけないなって改めて。
子どもは親の姿を見て学ぶ生き物。
時代に沿って自分も成長し続ける
それが子どもの羅針盤となり
家庭での学びを支える土台になると信じて。
私も子どもも「学び」を楽しめるように。
よし、対話スキル上げていこう。
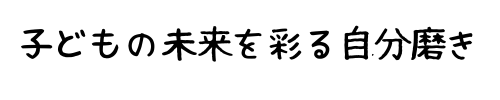

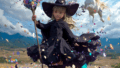

コメント